大慈寺創建と秋田征伐さてこの大慈寺が新しくつくられた背景には、 根城の殿様の秋田への出陣が深い関わりが あったのでした。 応永年間の頃、根城の殿様の本家筋にあたる 三戸南部家は、南北朝時代の初期一時勢力が 衰えていたのですが、十三代の守行の時代には、 陸奥の国司職になっていました。 その守行が、根城の九代目の殿様の長経を 三戸に呼んで相談しました。 (近頃しばしば隣国の秋田の領主安東氏の 軍勢が、我が南部の領地を侵している。 これを征伐するため出陣をすることにした。 その後の領内の警備を、根城南部家に お願いを致したい) ということでした。 これに対して長経は、きっぱりと返事を しました。 (根城南部家は、三戸南部家のご配慮により、 足利将軍から取りつぶされずにすみました、 そのお礼のためにもこの度の出陣には、 我が家の若い光経を先陣として参加をさせて くださるよう、お願いもうしあげます) 守行はこの申し出を喜んでうけました。 長経は根城にもどり、早速秋田征伐の準備に とりかかりました。
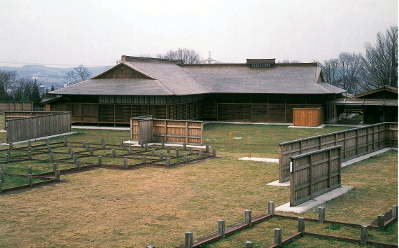
応永十八年(1411)元旦には、櫛引八幡宮に 参拝し、秋田征伐の武運を祈願しました。 この時先陣の大将をつとめる光経は、勝利を おさめ帰国した時には、着用の鎧かぶと 奉納すると共に、流鏑馬(やぶさめ)の神事を 神社の境内で毎年行いますと、神前に 誓いました。 応永十八年一月二十日、南部光経は軍勢を 引き連れて根城を出発、秋田を目指して 出陣をしました。 ところが地の利をしめて陣を張った秋田勢は、 逆に南部領の鹿角の郡内に「秋田領」と刻んだ 切り石を立てたりしました。 (その地は切石と言う地名になったとの事)
